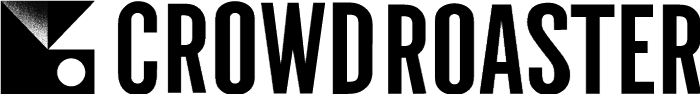見逃されがちだった焙煎の重要性
焙煎とはコーヒーの生豆に熱エネルギーを加えて煎ることである。一見、シンプルな行為だが、数多ある方法やその焙煎理論の幅広さからも、その奥深さは計り知れない。
焙煎前の生豆は淡緑色で、コーヒーらしい味も香りもなく、そのままでは飲むことができない。焙煎をすることで、いつも目にしている茶色いコーヒー豆へと生まれ変わる。人手によって管理されたコーヒー畑によって収穫された豆は、最終的にやはり人手によってようやく飲むことが出来る状態へと変化するのである。
コーヒー独特の風味は、豆に含まれる成分が加熱されて化学変化が起きることで生まれ、元は青臭い生豆も、焙煎することで香ばしい香りや、コク、甘味、酸味といったコーヒーの味わいやまるでフルーツや花々、穀物にも似た独特なフレーバーが作り上げられる。また、加熱時間や熱の加え方によって引き出されるフレーバーは驚くほど大きく変わる。
ここまで述べたことは、知っている方には当たり前のことかもしれない。しかし改めて考えてみると、コーヒーの生豆にはフレーバーも色も香りもない。ということは、コーヒーの特徴というものがまったく存在しないということである。
私たちが、日々楽しみ、周りのコーヒー好きたちとあれこれ批評めいたことを話し合い、コーヒーショップで注文する1杯のために真剣に検討する、あのフレーバーや質感やボディといったものは、焙煎してはじめて現れるものなのである。
これを再確認すると、焙煎がコーヒーを生み出す工程の中で、もっとも大切なものといわれていることも、当然だと思えるのではないだろうか。
焙煎のコントロールが緻密化

コーヒー文化の大きなうねりとなったいわゆるサードウェーブ以降、焙煎はさらに注目を集める分野となっている。
SEEDからCUPにおける多くの工程で、それぞれのプロフェッショナルが注目されるようになるなか、焙煎士という存在が、これまで述べた通り、コーヒーの味わいづくりに大きな役割を担うことがより明確になった。
例えば、焙煎度の選択、引き出すフレーバーへのフォーカス、質感やボディの出し方など、浅煎りから深煎りまでの焙煎方法が研究され、それらのコントロールが可能になりつつある。
スペシャルティコーヒーの分野では、そのコーヒーの持つ味わいをより明確にするために浅煎りが好まれるが、浅煎りでもフレーバーや香りがしっかりと引き出される手法が確立されてきたことで、可能になった。
そこには焙煎機の機能向上という要因もあるが、やはり焙煎士と呼ばれるプロフェッショナルたちが、試行錯誤し技術を手に入れてきたという面が大きい。
焙煎という新たな表現
今やコーヒー豆の品種は数多くあり、精選方法も多様化しているなか、コーヒーの銘柄は数え切れないほどあるといっても過言ではない。農産物である珈琲は、その年によって特徴が異なるため、毎年まったく同じクオリティや同じフレーバーを持ったコーヒー豆が出来上がることはない。
焙煎士たちは、そんな一期一会のコーヒー豆と真剣に向き合い、自分なりの解釈をし、焙煎を通して、コーヒー豆に想いを乗せる。
焙煎の完成度にとって、もちろん生豆自体のクオリティも重要ではあるが、焙煎士の感性や技術、環境、多くの要素が絡み合い、一杯のコーヒーが生み出されるのである。わずかな要素の違いで、味わいが変わるコーヒーは、焙煎士によって創り上げられる味わいが違うのは必然である。
卓越した技術と、それぞれの感性や哲学を掛け合わせ、焙煎という行為で表現をする焙煎士。それはまさに焙煎という名の新たな表現であり、「アート」であると言えるのではないだろうか。

CROWD ROASTERが提案する新たな楽しみ方
自然の営みと人の手が生むコーヒービーンズ。丁寧に作り上げられてきた赤い宝石を、「アーティスト」であるロースターが、ポテンシャルを最大限に引き出すために焙煎をする。
この過程こそが、さまざまなコーヒーの愉しみを生み出す。
コーヒー豆と焙煎という、その大切な要素を組み合わせることで、いままでにない一杯を生み出せないか。
CROWD ROASTERは、コーヒーを愛する方に向けて、味わいを左右する高品質なコーヒー豆と、哲学と技術をあわせもった焙煎士、それを自由に組み合わせることで、新たなコーヒーの楽しみ方を提案しています。
アプリをダウンロードして、新しいコーヒーの楽しみ方を手に入れよう。
この過程こそが、さまざまなコーヒーの愉しみを生み出す。
コーヒー豆と焙煎という、その大切な要素を組み合わせることで、いままでにない一杯を生み出せないか。
CROWD ROASTERは、コーヒーを愛する方に向けて、味わいを左右する高品質なコーヒー豆と、哲学と技術をあわせもった焙煎士、それを自由に組み合わせることで、新たなコーヒーの楽しみ方を提案しています。
アプリをダウンロードして、新しいコーヒーの楽しみ方を手に入れよう。
TEXT:TAKUROW TOMITA